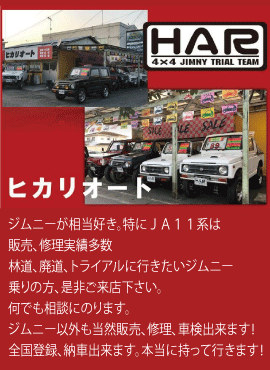ペンキ缶で自作していたオイルキャッチタンクver.2ですが、ニップルの付け根からブローバイガスが漏れる状態が発生したため外していました。
最大の原因はボディーに使っているペンキ缶の薄さです。
ニップルを後ろからボルトで固定していますが、鉄の板が薄すぎてしばらく使っているとニップルががたついてきます。
もう少し肉の厚い金属の筒状で密閉できるものはないだろうかとホームセンターを物色しましたが、ピンとくる素材がありません。
そのまま、車検を機に外していました。
そんな折、某ブロクでハンダでペンキ缶にニップルを付けている記事を目撃し、まねしてみることに。
バージョン3のボディもやはりペンキ缶です。
ニップルを付ける場所はバージョン1と同じ蓋上部としました。
また、溜まった油や水を排出する穴をボディ下部にあけて小さめのニップルを付けることにします。
ニップルはバージョン2のものをそのまま流用します。
まず蓋に2ヶ所穴を開けます。
ドリルであけましたが直径が15mm必要なので、あけた穴にラジオペンチを突っ込んで15mmの穴に拡張します。
予定の大きさになったらニップルをねじ込んでみます。
OKばっちり!
ここからが今回のミソです。
ロウ付け用の金属棒とバーナーを使い、ニップルとペンキ缶の蓋をロウ付けします。
まずはロウ付け部分にスラックスをまんべんなく垂らします。
あとは鉄の部をバーナーであぶって溶かし、ニップルと蓋の間を埋めてゆきます。
初めてのロウ付けだけあって、なかなか難しいです。
ハンダが水のように広がって、なかなかニップルの廻りに盛り上がるようには付いてくれません。
悪戦苦闘しながらも何とか2ヶ所のニップルの周りを鉄でロウ付けしました。
手で回してみてもビクともしません!ばっちりと蓋にニップルが固定されています。
続いては廃油用のニップルです。
缶下部に8mmの穴を開けて小さなニップルを差し込み、こちらもロウ付けします。
外が丸いので、蓋のロウ付け以上にむずいです。
付けては水を入れ、漏れる。。。を繰り返していくうちになんとか水が漏れない状態で固定できました。
これでボディーとニップルの固定は完了です。
バーナーの熱でボディが焦げているので塗装しようと青色のスプレーを吹きかけると
塗料が弾きまくりました、、、、脱脂&足付けが必要でしたが焦ってしましましたorz
仕方ないので、1度スプレーした状態で乾くのを待ち、ペーパーで全体をこすってから再度塗装しました。
次にオイルキャッチタンクのイン側内部に10comくらいのホースを取り付けます、蓋をします。
オイルキャッチタンク三代目の完成です!
クオリティーは1代目、2代目と比べるまでもなく高くなっています(但し見た目は相変わらず今ひとつですが)
あとはボンネット内部に固定してホースをつなげば完成です。
設置場所、1代目はラジエーターの右手に、2台目はエンジンとエアクリーナーの間に設置していましたが、今回はラジエータ左側のスペースに設置してみました。
汎用金具をリレーがとめられている金具にボルト止めし、その金具に金属バンドで固定します。
ホースは内径15mmのホームセンターで売ってる耐熱耐圧耐油ホース(10com58円)です。
今回は1,3メートル購入しました。
緑色のままではまったくいけていないので、オイルキャッチタンクと同じ青色でホースも塗装します。